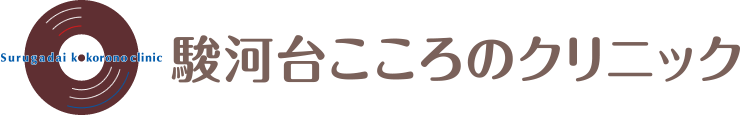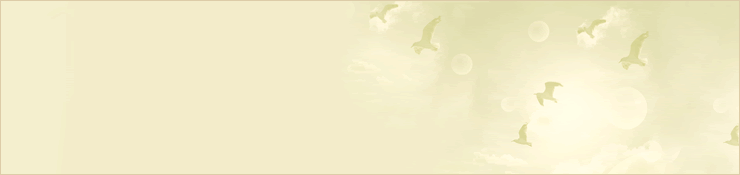レパートリーは多い方がいい
2016年08月27日
こんにちは。
「嫌なことがあった時、ストレスがたまって気分転換をしたい時、どんなことをしますか?」
と尋ねてみると、意外に返ってくる答えは少ない。
友人に相談する、音楽を聴く、酒を飲む、ジムに行く、旅行に行く、お菓子を食べる、寝る…
ストレス対処行動のことをストレス・コーピングと言います。これは、レパートリーがたくさんの方が良いです。
友人に相談しようと思ったけど仕事が忙しそう、酒を飲みすぎて体調が心配、旅行になかなか行けない…こうなると、ストレスはたまっていくばかり。
手軽にでき、お金もかからない方法をたくさん考えておくと良いと思います。あれをやってダメならこれ、といった感じに。
レパートリーを増やしてみてください!
薬物治療について再び その2
2016年08月22日
こんにちは。
前回の続きです。前回は薬の副作用のことなど書きました。
薬を使いたくない理由として、副作用、薬に頼りたくない、学校や職場で飲みにくいなどをよく耳にします。
できるだけ薬を使わない治療方針ですが、病気の種類や状態によっては薬を使わなければならないこともあります。
重度のうつ病でやる気がでない、悲観的になる、自分を責めてしまう、さらに自殺も考えているような場合、抗うつ薬などの薬物治療は必須です。もちろん、気持ちのサポートや環境調整などの精神療法やカウンセリングも不可欠ですが、あまりに重度で混乱している時は、薬物治療と休息が治療の中心となります。薬物治療8から9割、その他の治療1から2割のようなイメージです。
ところが、動悸がして電車に乗れないなどのパニック障害、手洗いや戸締まりの確認を繰り返してしまうといった強迫性障害では、薬物治療だけでなく認知行動療法が必要です。重症度にもよりますが、薬物治療1から2割、認知行動療法などが8から9割でしょう。
ある日、電車でパニックを起こしてから、電車に乗ると動悸がするようになった。外の景色がみえない地下鉄はダメ、事故などで急に止まるのが不安、最初にパニックを起こした○○線、○○駅は絶対ムリ…と言う方がたくさんおられます。
認知症にでもならない限り、パニック発作を起こしたという記憶が残っています。その記憶から電車への恐怖感や不安感が作られますが、記憶をなくす薬はありません。ですから、薬物治療だけで再び電車に乗れるようにするのは困難です。電車に乗るという訓練が必要です。
この訓練(行動療法)の際に、薬物治療を併用します。記憶を消すことはできませんが、不安感を少なくする効果があります。あくまで行動療法が中心的な治療です。
薬に頼りたくない。
薬について正確な情報を持っていない場合や、真面目でがんばり屋な方は、できる限り自分の力で、と考えます。
ですが、主治医から薬についてしっかり説明を受け、薬の力もうまく利用してみてください。
昨年のブログにも書きましたが、足が弱ったからといって散歩をあきらめるより、杖をついてでも外に出た方が良いと思います。
薬は杖のようなものなのです。
薬物治療について再び その1
2016年08月19日
こんにちは。
「できるだけ薬は使いたくない」
「薬を使い始めるとやめられなくなるのでは」
このように、薬物治療への不安を持っている方がたくさんおられます。
薬物治療については、2015年2月にも書きましたが、もう一度お話します。
薬は最小限にというのが当院の方針です。
薬にはメリットとデメリットがあるからです。
不安、不眠、気分の落ち込みなどの症状がある場合、考え方の修正や環境の改善、生活習慣の見直しなどによって改善するかどうかを見極めます。
また、薬を処方した場合、必要以上にたくさん使うなど薬を適切に使用できるかどうか、という点も重要です。
それから、薬の副作用を考えます。薬の多くは肝臓で代謝されますから、肝機能はどうか、生活に影響するような眠気は出ないか、便秘は・・・など。
結婚や出産を控えている女性の場合は、投薬は特に慎重に行います。正直なところ、薬は使いたくありません。
依存性についてもよく質問されます。
依存性に特に注意しなければならないのは、ベンゾジアゼピン系という種類の睡眠薬と抗不安薬です。薬理学的な依存性とともに、使用する状況的にも依存を形成しやすいからです。
電車の中で「また発作が起こったらどうしよう」といった予期不安が強い場合、必要以上に薬を飲んでしまうことがあります。そして、薬に頼りきってしまいます。
この「不安」という症状が強いと、拠りどころとなる「薬」を手放しにくくなる傾向があります。
抗うつ薬にも依存性はあります。
抗うつ薬は、意欲や気分の改善だけでなく不安症状に対しても効果があります。それから、SSRI(セロトニン再取り込み阻害薬)と呼ばれる薬などで、減薬の途中でイライラ、落ち着かないなどの症状が出る場合があります。これは、禁断症状のようなものです。精神的には依存していなくても、このような身体依存を形成していることがあります。
このように、薬物治療の必要性、服薬遵守や副作用面など安全な使用ができるかどうかなど、使い始めから減薬までを考えながら判断していきます。
次回につづきます・・・