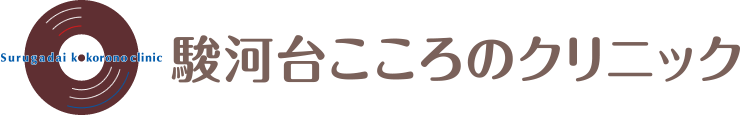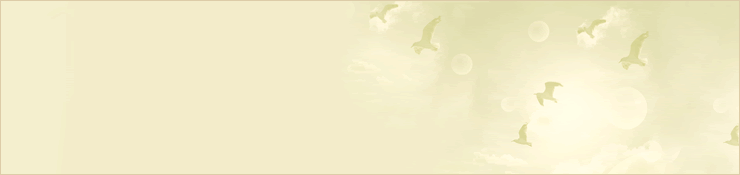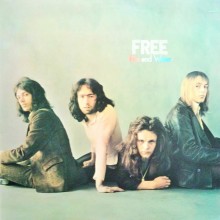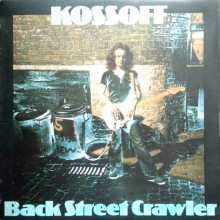泣きのギター♪
2015年02月19日
こんにちは。
ここでまた、少し息抜きです。
中学時代、ロックの師匠からKISS、Deep Purpleについて指導を賜ったロック少年は、高校でまた別の師匠に出会いました。彼から毎日のようにレコードを貸してもらいました。Black Sabbath、Boston、Rainbow・・・そしてFreeです。
1960代は、The Beatlesに始まり、多くのロックバンドが誕生したロック史にとってとても重要な時代です。特に後半には、プログレッシブ・ロック、サイケデリック・ロック、ブルース・ロック、そして実験的な試みも含めてさまざまなロックのスタイルが生まれました。
当時イギリスでは、ブルースなどアメリカの黒人音楽への憧れと崇拝の機運が高まり、それに合わせるようにEddie Boyd、Champion Jack Dupreeなど多くのブルース・マンが渡英、イギリスのミュージシャンと共演しました。そして、たくさんのブルース・ロックバンドが誕生しました。Freeもその中の1つです。
Freeは、平均年齢20歳の4人メンバーで1969年にデビュー。1971年、72年には来日し、当時日本でも人気があったバンドです。ボーカルのPaul Rodgersは、とてもソウルフルでロック界最高のボーカリストの一人と言われています。Free解散後は、ドラムのSimon KirkeとともにBad Companyを結成、その後Freddie Mercuryの後釜としてQueenにも参加しています。
ロック少年は、Freeの特にギターのPaul Kossoffに惚れ込んでしまいました。 速弾きではなく、むしろ音数は少ない。リズム感はあまり良くなく、上手いか下手かというと多分下手なんでしょう。しかし、まるで魂の叫びのようにギターが泣いています。Freddie Kingばりにチョーキングとビブラート奏法を多用します。ビブラート奏法は、ギターの神様Eric Claptonが教わりに来たほどです。
泣きのギターで分かりやすい曲は、昨年のソチオリンピックで羽生結弦選手がプログラムで用いたGary Mooreの「パリの散歩道」です。キュイーンという長いチョーキングを聴くことができます。
Freeは、7枚のアルバムを残し、3枚目のFire and Waterがイギリスチャート2位を記録するも、Paul Kossoffの薬物問題などで3年で解散しました。
諸説ありますが、あれだけ個性的で魅力的な演奏ができたにもかかわらず、同時期に活躍していたPeter GreenやEric Claptonと比較し、自信を失い薬物の量が増えていったようです。また、ヒットした3枚目のあと、渾身の4枚目が不評であったことも原因とされています。1、2枚目はブルースを基調としたゴリゴリしたアルバムでしたが、3枚目以降、ヒットを意識したアメリカン・ロックに次第に変わり、ブルースギターの出番が少なくなっていきました。
そして、 追い打ちをかけるようにFreeが解散し、さらにヘロインなどの薬物にのめり込んでいきました。”きめた”状態でステージにあがったり、ライブがキャンセルになったりを繰り返していました。そんな中、1973年にソロアルバムBack Street Crawlerを発表します。当時のガールフレンドが撮った写真が表紙になっています。
1975年に、再起をかけてソロアルバムと同名のバンドBack Street Crawlerを結成します。しかし、薬物の問題は深刻で、同年には心停止となり入院治療を受けています。奇跡的に復帰するも、1976年3月、飛行機の中で急逝しました。25歳でした。
既に録音を終え、同年発表予定であった最後のアルバム2nd Streetの裏表紙には「Dedicated to Koss」(Paul Kossoffに捧げる)と書かれています。最後の収録曲Leaves in the windは泣きのギター全開です。実際のライブをみてみたかったなと思います。
Freeを知って30年以上になりますが、今だに飽きることなく聴いています。 今では、イギリス在住のFreeファンとも友達になり、日本の音楽雑誌を送ったり、CDを送ってもらったりしています。
生前彼が、自分の音楽が後世でどのような評価を受けるのかなど知る由もなかったでしょうが、The Beatlesにしても世代を超えて、しかもいろいろな国で聴き続けられているなんてすごいことです。
ほんと、音楽っていいですね・・・
薬漬けにされる? その2
2015年02月18日
こんにちは。
昨日の続きです。前回、薬物治療への抵抗感についてお話してきました。
最大の理由の1つは、「薬漬けにされるのでは?やめられなくなるのでは?」という心配です。
ところで、「薬漬け、やめられなくなる」=「薬物依存になる」ということでしょうか?あるいは、=「飲み続けなければならなくなる」という意味でしょうか?
まず、「薬を飲み続けなければならない」ということについて考えてみます。
例えば、胃潰瘍という病気でみてみます。元々胃酸の分泌が多い体質だと、胃酸が胃壁を攻撃し続けますから、胃酸を抑える抗潰瘍薬を飲み続ける必要があります。もちろん、ストレスをためない、刺激物を控えるなど薬物治療だけで治すわけではありません。高血圧や糖尿病も同様で、これらの病気は脳梗塞や心臓病の原因になるのでしっかりとした治療が不可欠です。そして、いずれも慢性的な経過をたどる病気ですから、著しく病状が悪い時期を過ぎたのちも、再発予防の意味を含めて、どちらかというと薬を飲み続ける必要が出てきます。このように、飲み続ける必要のある薬は他にもあるのです。
睡眠薬や安定剤の作用をみてみましょう。単純に考えると、眠れないのは神経が昂っていることが原因で、神経を興奮させる物質が多い、もしくは興奮を鎮め眠りに誘導する物質の働きが弱いことが影響します。気持ちの落ち込みは、意欲、感情に関わるホルモンの不足です。そして、これらの不足したものを補い、働きを整えるのが睡眠薬、安定剤の作用です。
不足しているものを補い、働きを整えるという作用は、他の治療薬ものと何ら変わりありません。そして、長期に服用する薬は他にもあるのに、睡眠薬や安定剤だけが悪者にされるのは、こころの病や治療薬に対する知識不足や偏見とも関係しているのだと思います。
今度は、「薬を飲み続けなければならない」理由について考えてみます。
もし、安定剤を長期に使用している方がいたとします。その理由として、いくつか考えられます。①病気の特性上長期服用が望ましい場合、②治療薬の効果が不十分なため治療が長引いている、③不安や不眠などの症状が現れる原因、つまり心配事などが解決していない、④処方薬依存、などです。
①について分かりやすい例は、認知症です。アルツハイマー型などタイプは様々です。現在のところこれを完治させる薬は、まだ開発されていませんが、進行を遅らせる効果のある薬があります。このように、慢性的な経過をたどる病気に対しては、長期的な薬物治療が必要と考えます。
一方で、入学試験のことが気になって眠れない日が続いている方に、睡眠薬を処方するとすれば、一時的なものとなるでしょう。
それから、こころの病はその人の本来の性格や行動パターンなどと結びついていることが少なくありません。
うつ病の症状が改善したのちも、悲観的な考えを持ちやすい、几帳面で完璧主義という性格で人一倍仕事を頑張り過ぎてしまうことが続けば、症状は再燃(再発)しやすくなります。これまで、怒りのコントロールでもお話したような「信念」に基づいた思考と行動パターンを変えていく試みを怠っていると、症状は慢性化し、薬が手放せないことになるかも知れません。
睡眠薬や安定剤には種類がたくさんあります。そして、最大何㎎まで使用できるという限界があります。症状に合わせて治療薬を選択しますが、初回投与量から始め、効果が不十分な場合、量を増やします。最大量まで使用したり、ある程度の期間の効果をみて、他の薬剤に切り替えます。睡眠薬の効果は、その日から現れますが、抗うつ剤などは効果が現れるのに最低でも2、3週間から1か月を要します。このように、治療薬の効果を判定するためには、十分な使用量と使用期間が必要です。
②のような状況になる原因として、服薬への不安から、薬を飲んだり飲まなかったりする、通院をやめてしまう、主治医に症状が正確に伝えられていない、などが考えられます。
次に、③についてです。例えば、指にとげが刺さって痛い時にどうしますか?
とげはそのままにして、痛み止めを飲むでしょうか。まず、痛みの原因となっているとげを抜くのが通常の対処法です。もし、とげを抜いても痛みが取れないとなれば、場合によっては痛み止めを飲むことはあるかもしれません。
こころの問題も同じです。もし、症状に結びつく具体的な原因があれば、その解決が先決、もしくは薬物治療と同時に取り組む必要があります。きっかけが大切な人との死別であるなど、元に戻すことのできない状況ももちろんあります。その場合、こころのケアは不可欠で、薬物治療は補助的な意味しかないかも知れません。
もし、ここで具体的な原因への対応やこころのケアが十分になされないまま、薬物治療だけで何とかしようとすれば、治療効果が不十分なまま、長期間服用することになるでしょう。
次に、④の処方薬依存です。
最近、薬物依存の原因薬剤として、アルコール、覚せい剤、危険ドラッグ、とともに処方薬が大きな問題となっています。
当科で使用される治療薬の中でも、特にベンゾジアゼピン系と呼ばれる種類の睡眠薬や抗不安薬にはある程度の依存性があります。 睡眠薬を長期に使用することで、薬を使わないと全く眠れない、効果が薄れてくるなどの状態になることがあります。
しかし以前、「寝酒がよいか睡眠薬がよいか・・・」でもお話ししましたが、長期間睡眠薬を飲んでいる方が、ある日突然ぴったり睡眠薬を使わず寝るというのは難しいですが、徐々に止めていくことは可能です。また、依存性の少ない薬剤に置き換えるという方法もあります。また、抗うつ剤、抗精神病薬と呼ばれる薬剤は、比較的依存性は少ないと言われています。
不安になった時に、抗不安薬を使用している人は、お守り代わりに薬を持ち歩いていたり、調子が悪くなるかもしれないと先回りして服薬をするあまり、薬の量や回数が増えていくことがあります。不安を感じるきっかけに始まり、マイナスの思考から、不安発作などに発展するとすれば、認知行動療法と呼ばれる手法などで思考の修正を併用することで、必要以上に服薬量が増えるのを抑えることができる場合があります。
依存のさらに細かい部分については、またいつかお話しようと思います。
薬を飲まないで生活できるのがもちろんベストだと思いますが、病気にはならずとも、誰でも年齢とともに体力、気力などの衰えは現れますし、体質も変化していきます。その時々の状態に合わせて、心身を整える1つの方法が薬物治療だと思います。
「最近、足腰が弱ってきた。だけど、散歩がしたい。じゃあ、杖をついて歩くか。」
杖を使うのと同じように、自分がやりたいこと、やらなければならないことを実行するために、薬の力を借りる。そう考えた方が、得られることが多いように思います。
また、指示に従って適正な使用に心がける、何かあればすぐに薬ではなく、その都度必要かどうかを吟味して使用すれば、依存性の問題もクリアできると思います。
長文失礼いたしました・・・
薬漬けにされる? その1
2015年02月17日
こんにちは。
前回、心療内科・精神科の受診をためらう理由にいくつかあるというお話をしました。
今回は、その続きで「薬漬けにされるのでは?薬がやめられなくなる?」ということについてお話をします。
当科の治療は、精神療法、薬物療法、その他の治療法の大きく3つに分けられます。精神療法は、個人か集団かに分けられ、手法として認知行動療法、精神分析などいくつかのものがあります。その他の治療法には、電気けいれん療法などが含まれます。そして、薬物治療です。
薬物治療には、内服、注射(筋肉、静脈、点滴)、坐薬といういくつかの投与方法があります。内服が難しい場合や特に即効性を期待する場合、注射や坐薬を使用します。当院のようなクリニックの場合は、内服薬の処方が中心です。
疾患の種類や症状の程度によって、薬物治療が第一選択となることがあります。特に、興奮、幻覚(存在しないものを知覚すること)、妄想(訂正不能な誤った考え)などが著しい場合です。このような状態になると、自分や他の人を傷つけたり、事件や事故に巻き込まれたりする可能性が高くなるからです。
一方、不眠、不安などが主な症状で受診された場合、必ずしも薬物治療がすぐに始まるとは限りません。就寝前にコーヒーなどの刺激物を摂取している場合、コーヒーを控えることで不眠が改善することもあります。また、問診するだけで解決の糸口がみつかり、不安症状が治まることも少なくありません。
当院では、薬物治療が必須の状態を除いては、睡眠薬、抗不安薬(いわゆる安定剤の1つ)、抗酒剤(アルコール依存症の治療薬)などの効果、副作用について患者さんに説明したのち、処方を希望するかどうかを最初に確認しています。特に服用が初めての方は、副作用が気になり、不安、抵抗感があるのは当然のことだからです。
そして、不安に思う理由を確認します。「一度飲み始めると、一生やめられなくなるのではないか。認知症になるのではないか」、など誤解があれば説明を繰り返します。また、睡眠薬などは毎日ではなくて、眠れない時だけ頓服として服用する方法もあります、という提案もします。それでも、不安が拭い去れなければ、一旦薬物治療は見送ります。
抗うつ剤など、ある一定の期間決められた量を服用することで、はじめて効果が現れるものもあります。もし、服薬に抵抗感があると、薬を飲んだり飲まなかったりと不規則な服薬になり、十分な治療効果が現れないまま、「せっかく勇気を出して病院に行き、薬を飲んだけど治らない。もう病院には行かない。」と思い込み、さらに症状が悪化する可能性もあります。また、処方薬を貯め込んでしまう危険もあります。
ですから、薬物治療は「服薬した方が良いですよ」という提案と「でも不安。できれば飲みたくない。」という不安や抵抗感、必要性の折り合いがついた時に行われるのが基本です。しかし、先述の興奮、幻覚妄想が著しい場合には、注射薬を使用するなどかなり積極的な治療になることもあります。
さて、これから「薬漬け」について本題に入るところですが、前ふりが長くなり過ぎましたので、続きは次回お話します。